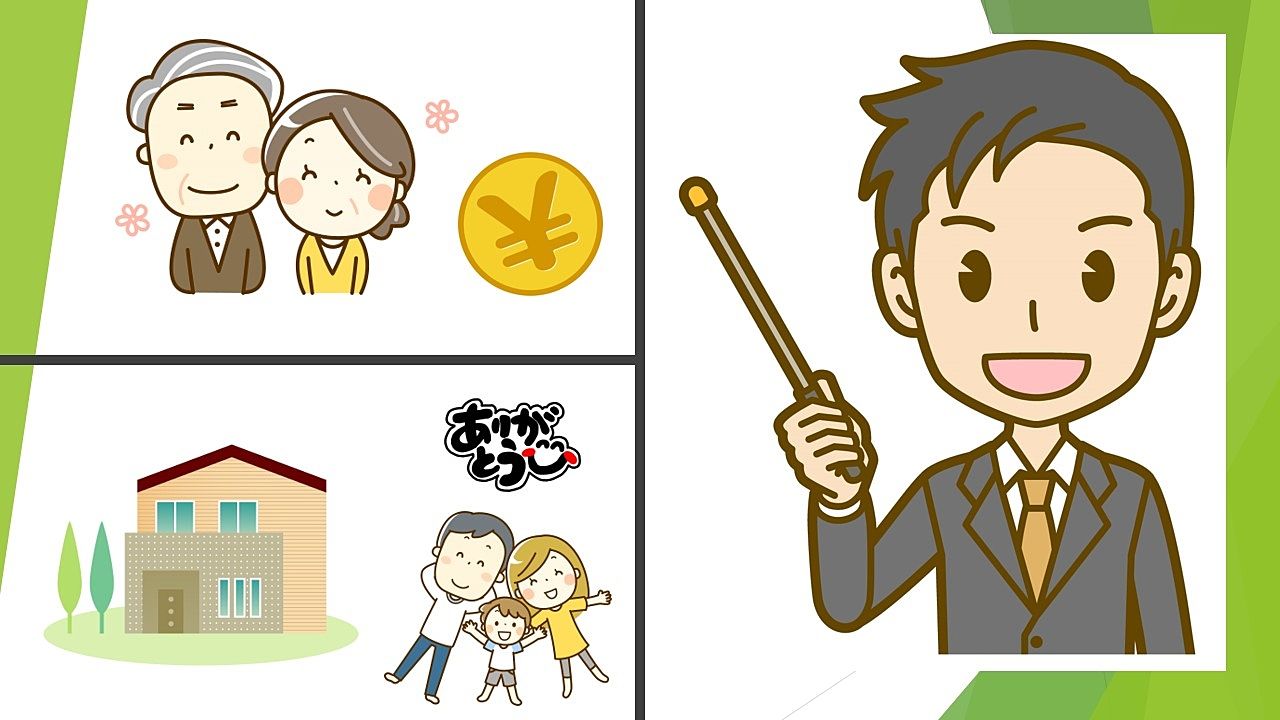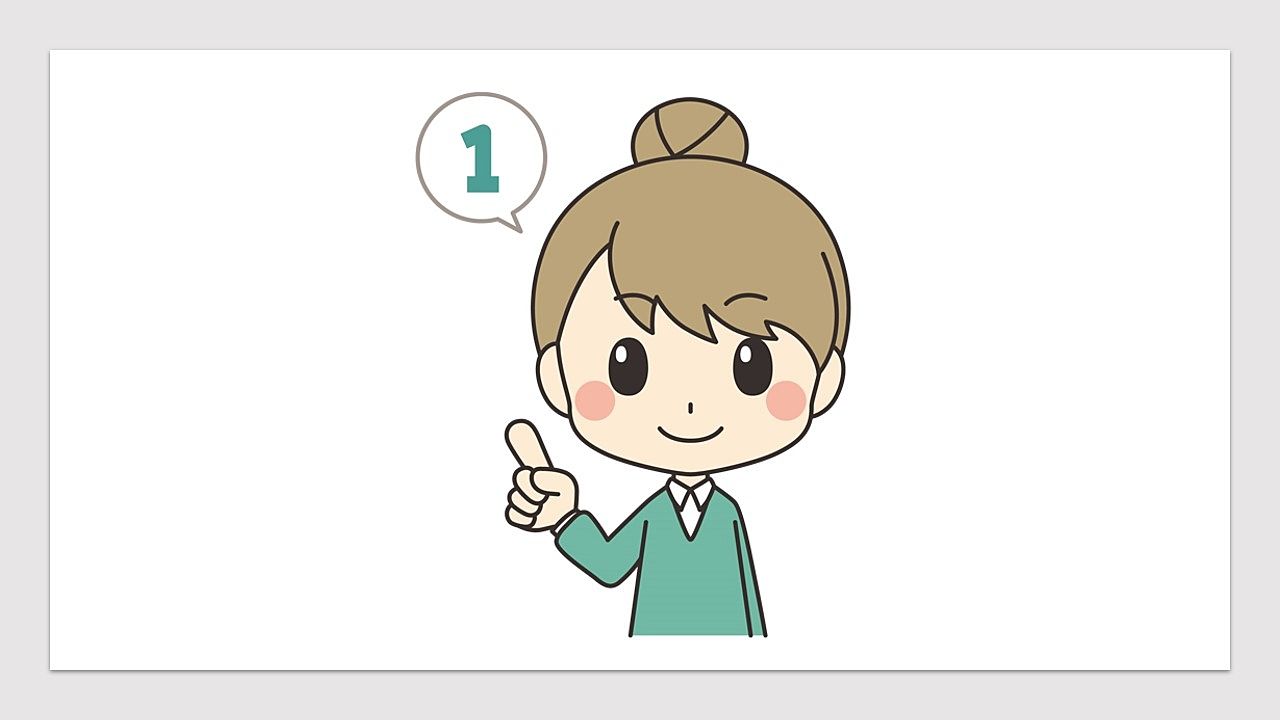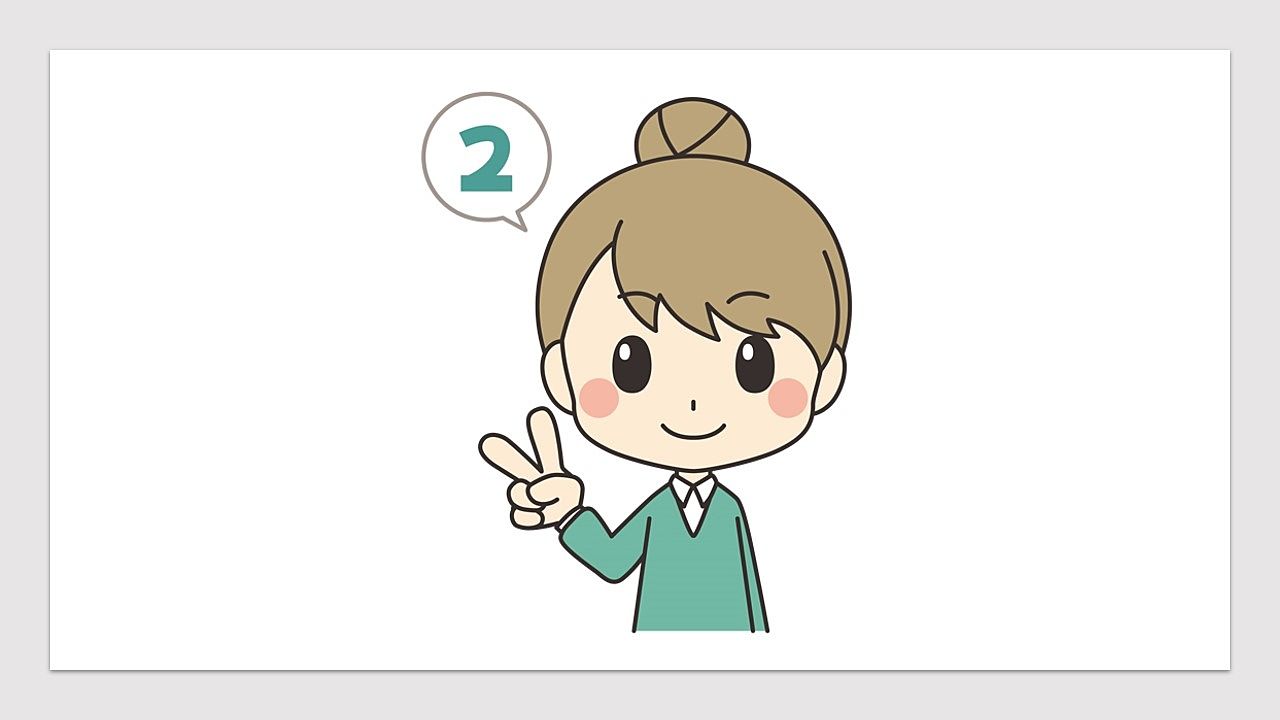両親・祖父母の援助を受けてマイホームを購入する3つの方法を解説します!
マイホームを買うとき、希望金額の住宅ローンの借り入れができなかったり、自己資金だけでは購入金額に届かないことがあると思います。よくあるケースは…年収は高いけど過去に返済の遅れがあって借入ができない場合、転職して年収が下がっている場合、産休・育休中で住宅ローンの審査が厳しい場合などです。
このような場合、両親・祖父母に援助をお願いするのも1つの選択肢になりますから、この記事で注意点を把握しておいてくださいね!
ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」
方法1:両親からお金を借りてマイホームを購入する
両親・祖父母の援助を受けてマイホームを購入する3つの方法を順番に見ていきます。
両親の援助でマイホームを購入する方法1…
「両親からお金を借りる」
税務署から贈与だと疑われる可能性がありますので、下記【1】~【5】の条件をしっかり守ったうえでお金を借りるようにしてください。
なお、「お金にゆとりがある時に返せばいいよ。」とか「返さなくてもいいよ。」と言ってもらえても安心したらダメです!贈与とみなされて高額な贈与税が課税される可能性がとても高くなりますからね。
【1】金銭借用書または金銭消費貸借契約書を作成
お金を借りる契約のことを、金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひたいしゃくけいやく) と言います。略して金消契約 (きんしょうけいやく) なんて呼んだりもします。
「金銭借用書」は個人間で利用し、「金銭消費貸借契約書」はもう少し堅いイメージで、銀行からお金を借りる場合に利用されるという違いがあるようです。どちらも個人で作成可能。手書きである必要もありません。「借入金額」「返済期間」「利息」などの借入条件を記載したら印紙を貼って消印しましょう。
金銭借用書は借主が貸主に差し入れる書類になります。貸主が原本を、借主がコピーを保管しますから印紙は1枚でOKです。
金銭消費貸借契約は借主・貸主が当事者として署名捺印する書類になります。原本を2部作成してそれぞれが原本を保管しますから印紙も2枚必要になります。
【参考1】金銭借用書・金消契約書の印紙税額
1万円未満 ⇒ 非課税
10万円以下 ⇒ 200円
50万円以下 ⇒ 400円
100万円以下 ⇒ 1,000円
500万円以下 ⇒ 2,000円
1,000万円以下 ⇒ 10,000円
5,000万円以下 ⇒ 20,000円
1億円以下 ⇒ 60,000円
【参考2】印紙の消印
印紙は消印 (けしいん) することで印紙税を納税したことになります。そのため、消印をしていなければ過怠税という罰金を科せられてしまいます。印紙貼り忘れの場合は印紙額の3倍、消印忘れの場合は印紙額と同額を支払うことになってしまいます。
消印は借主・貸主のどちらかが押印または署名で行えばよいのですが、できれば、借主と貸主の両方が押印するのが良いでしょう。印紙の上下左右どこに押印・署名しても構いません。
なお、二重線やチェックでは印紙を再利用できる恐れがあるため消印として認められません。注意しましょう。また、「消印」を「割印」と言っている人がとても多いですけど、間違いですよ~
【参考3】印紙の貼り間違い
印紙を間違って貼ってしまった場合、税務署で還付請求できます。ちなみに、ゆめ部長が税務署に相談した時は「契約書記載の当事者が直接税務署に来てください」と言われたことがあります。つまり、仲介会社は当事者ではないので還付できないということですね。注意してください!
結局どうしたかと言うと、消印する前で損傷もなく綺麗な状態だったので、金券ショップに相談してみたら、印紙額の80%くらいで買い取ってくれました。インターネットでは「換金できない」と書かれていることが多いですけど、諦めずにチャレンジしてみるのもいいかもしれませんよ。
【2】一定の利息は必要
貸付金の利息を無利息にしたり、極端に低い金利を設定すると、贈与税が課税される可能性があります。税理士先生に聞いてみましたら、0.2%くらいで設定すれば良いとのことでした。これは「社内ローンの金利を0.2%未満で設定した場合は給与になる」という基準からの考えになるそうです。
0.2%で借りられたら返済が楽になりますね!
【3】契約書に記載した返済日に毎月振込送金
「親子だから返済日に遅れてもいいや」という考えは危険です。毎月、約定日に振込送金して証拠を残しましょう。また、返済は借入した日の翌月から始めるようにします。
「2年くらい送金履歴を残しておけばその後は送金しなくても大丈夫。」という話を何度か聞いたことがあります。しかし、数年後に返済しているかを税務署が確認してくることがあるそうです。絶対に大丈夫とは言えないですから、しっかり返済することをオススメします。
【4】親が80歳になるくらいまでに返済
親の年齢を考慮して常識的な範囲内で返済期限を設定してください。
70歳の親に対して35年返済にしてしまうと完済が105歳になってしまいます。日本の平均寿命は延びていますけど「105歳はちょっと…」と思いますよね。
絶対に80歳までというわけではなく、85歳までに完済でも一応OKなようです。
【5】銀行の住宅ローンも考慮して、毎月返済可能な額で抑える
銀行で借入できる限界額まで住宅ローンを借りながら、両親からも3,000万円借りたら返済能力を超えて借り過ぎです。返済遅延・返済不能に陥らないような返済計画を立てるようにしてください。
住宅ローンの審査では、2つの基準「審査金利」と「返済比率」を使って返済できるかどうかを判断しています。
ある銀行を例に見てみましょう…
融資可能額の判断基準は、優遇後の金利(実際に適用される金利)が「3.3%」まで上昇したとしても、住宅ローンの年間返済額が「税引前年収×35%」に収まる範囲までとされています。
3.3%の金利 :「審査金利」or「算出金利」
税引前年収×35% :「返済比率」
一歩踏み込んで解説!
適用金利(基準金利-金利優遇)が審査金利(3.3%)まで上昇して35%以内ですから、実際の返済比率は35%よりもだいぶ低くなります。2020年現在では、金利優遇が2%前後あり、適用金利は0.4%~0.6%程度ですから、金利が2.7%~2.9%上昇して初めて返済比率が35%に到達するということになりますよね。しかし、これは「税引前」年収であり「手取り」年収ではないことにも注意が必要です。(解説・終)
ちなみに、税金の本には「年収×40%以内が目安」と書いてありましたけど、金利優遇後の適用金利で40%以内に収まっている…そんな状態では、金利が上昇したら返済不能に陥るのは間違いありません。金利上昇リスクも加味しなければいけないと思うのですけど…どうなのでしょうか??
方法2:両親から贈与を受けてマイホームを購入する
両親の援助でマイホームを購入する方法2…
「両親から贈与を受ける」
マイホームを取得する場合、一定金額まで贈与税を非課税にできる制度がありますので、両親から贈与を受けて購入することも検討しましょう。
下記のように2つの制度を併用することで最大4,000万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。計算式を記載しておきます。
住宅取得等資金の非課税制度 + 暦年課税の基礎控除
または
住宅取得等資金の非課税制度 + 相続時精算課税制度
・暦年課税 or 相続時精算課税のどちらか1つだけ加算OK
・3つの制度全部の合算はNG
・暦年課税 + 相続時精算課税制度もNG
2023年(令和5年)12月31日までの贈与に関する非課税限度額は次の通りです。なお、「建物消費税が10%かかる物件」or「建物消費税が非課税になる物件」で限度額が分かれていましたが、令和4年度からは統一されました。
住宅取得等資金の非課税制度:1,000万円 or 500万円
暦年課税の基礎控除 :110万円
相続時精算課税制度 :2,500万円
では、3つの制度を順番に見ていきます。
【1】住宅取得等資金の非課税制度
お父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんからマイホーム購入資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税を非課税にすることができる制度です。
お父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃん全員から贈与を受ける場合は、合計金額が下記の金額以内でなければ贈与税が課税されてしまいます。全員から500万円~1,000万円ずつ非課税で贈与してもらえるわけではありません。それぞれから贈与を受けられる相続時精算課税制度とは異なりますので注意してください。
まぁ、こんな裕福なお家に生まれているのであれば、専属の税理士先生がいるでしょうから問題ないと思いますけどね~(羨ましいーー!)
2023年(令和5年)12月31日までに贈与すると…
省エネ等住宅 :1,000万円
その他の住宅用家屋: 500万円
この金額までは贈与税が課税されません。
「省エネ等住宅」とは「住宅性能評価書」などで下記いずれかの基準を満たしていることが証明できる家屋を言います。
■ 耐震等級2以上(構造躯体の倒壊等防止)
■ 免震建築物
■ 断熱等性能等級4
■ 一次エネルギー消費量等級4以上
■ 高齢者等配慮対策等級3以上(専用部分)
なお、「省エネ等住宅」であることを既存の書類で確認できなかったとしても簡単に諦めないでください。2つの事例を紹介しておきますね。
新築一戸建てで住宅性能証明書を取得した事例
新築一戸建ての販売図面には、どこにも「耐震等級○級」・「一次エネルギー消費量等級○級」などの記載がありませんでした。住宅性能評価書を取得していない物件は多いので仕方ない…。しかし、よく見ると、備考欄に小さな文字で「贈与税非課税を利用するための証明書の取得は108,000円」と書いてありました。
担当者さんに質問してみましたら、調査を入れる必要はあるけど「ほぼ、間違いなく証明書を取得できますよ。」との回答でした。
ちなみに…「住宅性能評価書」と「住宅性能証明書」は別の書類です。
中古マンションで住宅性能証明書を取得した事例
平成25年に住宅性能評価制度の項目に変更があり「一次エネルギー消費量等級」ができました。そのため、平成25年よりも前に発行された住宅性能評価書では「一次エネルギー消費量等級」の記載がありません。
そこで、住宅性能評価書を発行した会社へ「省エネルギー等級4」を取得している当該マンションが「一次エネルギー消費量等級4」に該当するかどうか…?について調査依頼しました。
その結果、該当していることがわかり、「住宅性能証明書」を取得。「省エネ等住宅(良質な住宅用家屋)」として非課税制度を利用した経験があります。
この時は調査費用と証明書の発行で108,000円(消費税8%込)かかりましたけど、贈与税を考えれば安いものですね!
2019年10月追記…
「住宅取得等資金の非課税制度」は「住宅借入金等特別控除」と併用することができます。しかし、次の注意点がありますので十分に注意してください!住宅ローン控除の計算方法が変わり、次の計算式で求めた金額の小さい方が控除限度額となるのです!
■ 年末の住宅ローン残高×1%
■ (不動産購入価格-贈与額)×1%
具体例を見てみましょう。
両親からの贈与700万円・住宅ローン3,000万円で3,500万円の新築一戸建てを購入しました。3年目・年末の住宅ローン残高が2,900万円です。この年の住宅ローン控除限度額はいくらになるでしょうか…?
通常であれば、住宅ローン残高2,900万円×1%で29万円が控除限度額となりそうですよね。ところが、この計算式ではNGなのです。
700万円の贈与に対しては先に非課税となっているにもかかわらず、さらに住宅ローン控除で税金の優遇を受けていることになります。つまり、二重に優遇措置を受けてしまった…ということです。
そのため、実際の計算式は次のようになります。
(3,500万円-700万円)×1%=28万円
28万円 < 29万円
小さいほうの28万円が控除限度額!
この問題が生じるのは下記の場合です。自己資金が多くて住宅ローン借入額が少ないなら関係ないお話になります。
住宅ローン借入額 + 贈与額 > 不動産購入価格
平成30年12月11日に国税庁から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」がありました。ちょっと難しい内容ですけど、この項目の申告ミスが多発していることへの注意喚起でもありますから、興味があれば読んでみてくださいね。
2020年8月14日更新…
いつの間にか「良質な住宅用家屋」は「省エネ等住宅」へ変更されていましたので、名称を変更しておきました。
2022年2月11日更新…
建物の築年数要件が緩和され、登記簿の新築日が昭和57年1月1日以降であれば、この制度を利用できるようになります。
【2】相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、マイホーム購入資金の贈与税を非課税にできるという制度ではありません。相続発生時には「贈与税」のかわりに「相続税」を支払わなければいけないので注意してください。
贈与税の税率はものすごく高く、
相続税の方が税率は低くなります。
相続税が発生しないケースであれば、相続税も贈与税も非課税です。ただし、2,500万円以上の贈与を受けた場合は、超えた部分×20%だけ贈与税が課税されます。
この制度は暦年課税 (毎年110万円までは贈与税を非課税にできる制度) との選択適用になりますけど、住宅取得等資金の非課税制度とは組み合わせて使うことができます。先ほど、色を分けて記載した通りです!
方法3:両親も持分を取得してマイホームを共有する
両親の援助でマイホームを購入する方法3…
「両親も持分を取得して共有する」
子が住むマイホームを親子で共有します。この場合、親の持分を子は無償(タダ)で使用してOKなので家賃の支払いは不要です。
この方法は相続税対策としても有効になります。不動産は相続財産の評価では、実際の価格よりも安くなります。1,000万円の現金を不動産に変えると、評価額が400万円~500万円まで下がるため相続税が安くなるのです。
ただし、持分を持っている親が亡くなった場合、その持分を仲の悪い兄弟姉妹が相続するとメンドウなことにもなりかねません。この点には配慮が必要だと言えるでしょう。
これで解説は終了です!!
両親から援助を受けられる人ばかりではないと思いますが、皆さまが援助を受けられるラッキーな人ならば、税金対策としても1度検討してみてくださいね!
最後に…
税金はとにかく複雑で難しいですから、個別具体的な案件は必ず税理士先生へ相談するようにしてください。専門家への相談料はケチったらダメですよ!
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
参考記事…
“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…
— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日