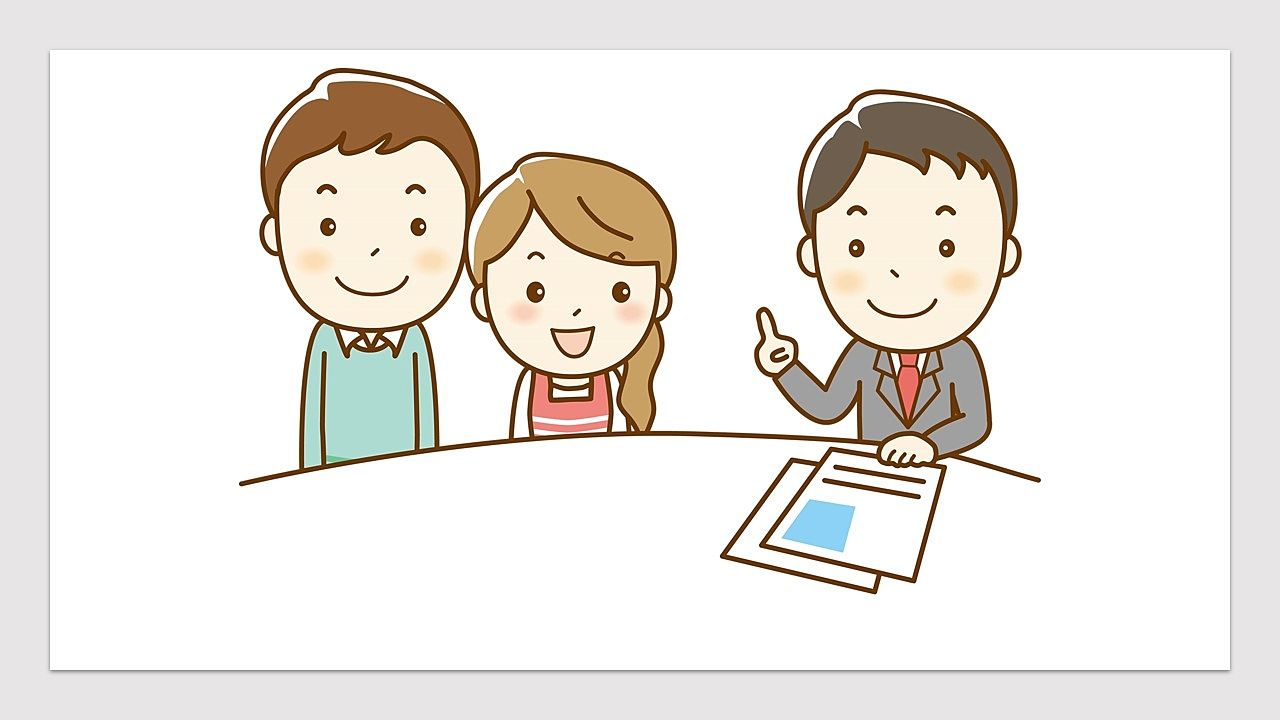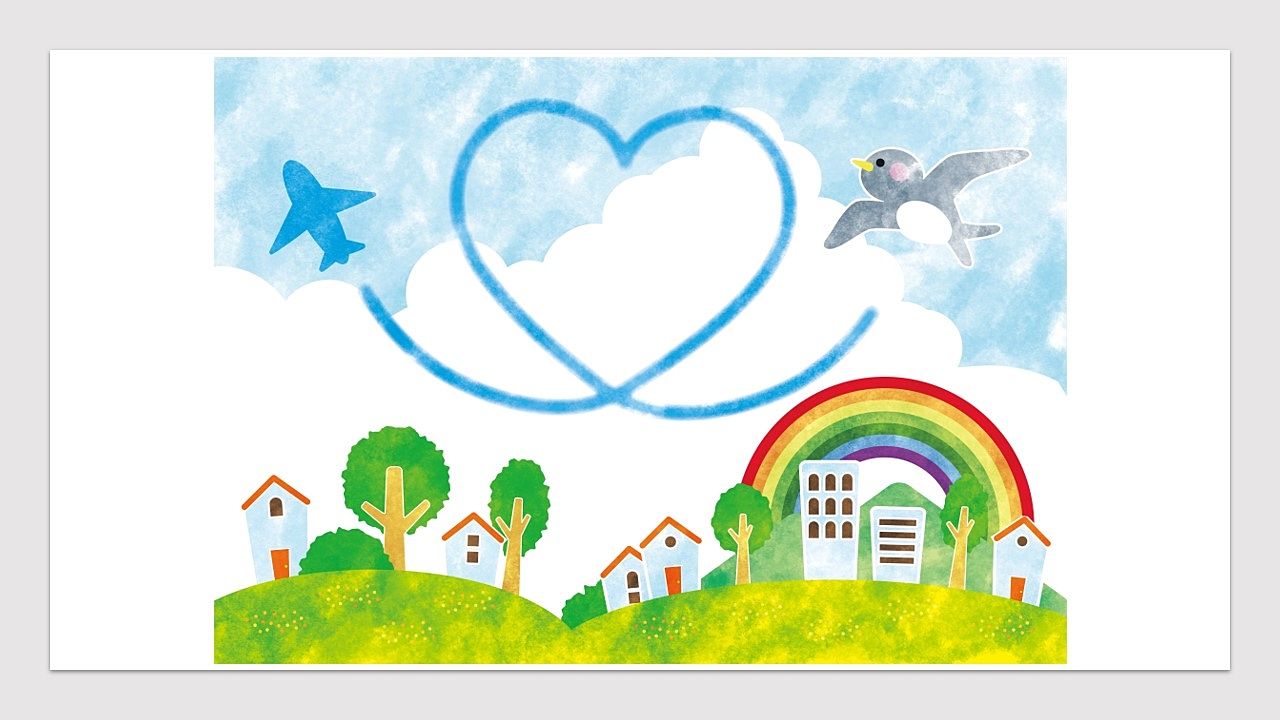不動産売買契約の「手付金」をわかりやすく解説!
不動産の売買契約を締結するときに支払う「手付金」がどういうものかわからない!というご質問がたくさんあります。そこで、手付金の妥当な金額・保全措置・法律の定めなどをわかりやすく解説してみたいと思います!
ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」
【 目次 】
1. 手付金の基本知識を抑えましょう
1-1. 売買契約とは別に「手付契約」を締結する
1-2. 手付金授受を契約成立のメルクマールとした判例がある
1-3. 手付金は売買契約の後に支払ってもいいの?
1-4. 手付金は振込ではなくて現金持参が原則
1-5. 手付金は売買代金の一部になるんですよね…?
1-6. 手付金の法的性格
2. 手付金の妥当な額・法律の規制・保全措置
2-1. 手付金額に関する法律の規制
2-2. 手付金の保全措置
2-3. 住宅ローンの残債 > 売買金額の場合
2-4. 手付金の妥当な金額
2-5. 少額手付契約の注意点
3. 最後に…
手付金の基本知識を抑えましょう
「手付金」とは、売買契約を締結する時に、買主さま から 売主さまに支払われる金銭のことを言います。手付金に関して知っておいて欲しいことがいくつかありますので、順番に見ていきましょう。
【1】売買契約とは別に「手付契約」を締結する
手付金の成立は「手付契約」によります。
「売買契約書」とは別に「手付契約書」があるわけではないため、不動産屋さんも手付契約について知らない人の方が多いと思います。
手付契約は売買契約に付帯する契約ですが、別個独立した1つの契約であり、手付金が現実に授受されることによって成立する要物契約(ようぶつけいやく)です。
契約書類で定められた額の手付金が必要なわけですから、手付金の一部が支払われたとしても手付契約は有効に成立しません。「手付の予約」があったに過ぎないと判断されるようです。
つまり、売買契約時に売買契約書で定められた「手付金全額の授受」が行われていなければ、手付契約は成立していないことになります。
【2】手付金授受を契約成立のメルクマールとした判例がある
「売買契約の成立」に関しては、裁判で争われることが多いのですが、私たちが実務をする上では次の2つが重要だと考えています。
■ 売買契約書へ売主さま・買主さまが署名・捺印をする。
■ 手付金の授受がある。
詳細は別の記事で書きますけど、不動産の売買契約は「買わせてください!」⇒「もちろん!よろこんで。」と、売主さま・買主さまの意思表示が合致するだけでは成立しないと考えられています。(売買契約に関する民法の原則とは異なるということ!)
いろんなWebページを読んでみると「売買契約書への署名・捺印だけで売買契約が成立する」と書かれているものが多い印象ですけど、平成21年2月19日・東京地裁判決では「手付金授受が契約成立のメルクマール(指標)になる」とされています。
不動産は高額な商品であり、頻繁に取引が行われるものではありませんから、慎重に取引が行われることを誰もが期待しますよね。
だからこそ、やむを得ない事情に備え、少なすぎず、多すぎないペナルティーで契約を解除できる「手付解除」は必ず入れておくべき項目だと思います。
ゆめ部長は次の流れで理解しています。
売買契約書に「手付解除」に関する規定があるけど手付金授受がない
⇒ 手付契約が成立していない
⇒ 手付解除できない
⇒ 慎重な取引な取引を実現できない
⇒ 売買契約も有効に成立していない
最初から手付解除に関する条文を削除していれば関係ないでしょうけどね。
弁護士先生の見解や宅建士テキストの記載などを別記事で紹介してあります。興味があれば読んでみてください!
参考記事…
【3】手付金は売買契約の後に支払ってもいいの?
手付金は売買契約時に全額授受しなければいけません。後払いにすると、売買契約と同時に手付契約が成立していませんから、お互いに手付解除できなくなってしまいます。
後払いしたお金は「中間金」や「内金」となり、手付金にはなりません。契約解除になった場合、手付金は没収されますが、中間金や内金は返却されることになるという違いがあるのです。
よくあるケースと対処法…
売買契約日の当日にATMで300万円の手付金を引き出そうとしたら「50万円の制限」があって全額おろせませんでした…。という買主さまを見ることがあります。この場合は仕方ありません。後日、手付金を振り込んでもらい、売主さまが着金確認を取れた時点で売買契約が有効に成立したことにします。契約書類の日付はブランクにしておきましょう。
もう1つ問題があります。
宅建業者(不動産屋さん)が売主として分譲したり、仲介(=媒介)するなら、手付金授受に関して次のような対応をすると「宅建業法違反」となります…
【宅建業法47条3号・信用供与による契約締結誘因の禁止】
■ 手付金を貸す
■ 手付金を立て替える
■ 手付金を後払いにする
■ 手付金を分割払いにする
宅建業法違反になりますと、行政罰・刑事罰を受けます。免許取り消しになったら大変ですから、わかっている不動産屋さんであれば、絶対にこんなことはしません。
宅建業法違反になる理由は… 不動産屋さんが買主さまを急かして契約させるのを防止するためです。「手付金は後でいいですから、これからすぐに契約しちゃいましょうよ!」と迫ってきた不動産屋さんは「アウト」になります!
【4】手付金は振込ではなくて現金持参が原則
手付金は振込でもOKとしている会社もありますけど、原則は、売買契約の場に現金を持参していただくことになります。理由は2つ。
理由1…
売買契約書への署名・捺印が終わってからすぐに振り込みをしたとしても、その日のうちに着金確認が取れるかわかりません。先ほども書きましたけど、売買契約を有効に成立させるためには、売買契約と同時に手付契約も締結するべきです。
理由2…
「現金持参が怖いから事前に振り込みたい」という要望も多いです。確かに、ATMでは1日50万円の出金制限がかかっていることがありますから、窓口に行って数百万円を出金するのは大変ですし、持参する時に盗難リスクもあります。しかし、売買契約が成立する前に数百万円を振り込むリスクもかなり大きいと思います。なぜなら、売主さまの本人確認が取れていない状況ですから、偽物の売主に現金を渡して持ち逃げされるかもしれないからです。
少し大変であることは理解できますが、親族の方と一緒にデリバリーするなど、対応策を検討してください。
どうしても振込にしたい場合は、上記のリスクがあることを了承してくださいね。
【5】手付金は売買代金の一部になるんですよね…?
手付金は大きなお金になりますから、もちろん、売買代金の一部に充当されます。ちょっと細かい解説をしますと…
手付金は残代金決済時(=引渡時)に返却されるのが原則です。しかし、大きなお金をいったん返却してもらうのはメンドウですから、売主さま・買主さまが合意して、売買代金の一部に充当するものとしています。
ゆめ部長が利用している(公社)全日本不動産協会の売買契約書では、不動産売買契約条項・第2条(手付金)で次の文言が記載されています。
1. 買主は、売主に対し、表記手付金を本契約締結と同時に支払います。
2. 売主および買主は、手付金を表記残代金支払いのときに、売買代金の一部に無利息で充当します。
結論だけ知っておいてもらえればいいかな…と思います。
【6】手付金の法的性格
手付金の法的性格というのは「手付金の法的な意味づけ」です。
手付金の法的性格は次の3つに分けられます。
■ 証約手付
■ 違約手付
■ 解約手付
該当するのは「解約手付」ですから、これだけ解説しておきます。
解約手付とは… 手付金額だけの損失を覚悟すれば、一方的な事情で売買契約を解除できるというものです。売主さまが「やっぱ売りたくないんだよね…」とか、買主さまが「もっと良い物件が見つかったからキャンセルしてそっちを買います!」というのが認められるわけですね。
民法では、契約当事者の意思で法的性格は決定され、明確な取り決めがない時は解約手付と「推定する」と定めています。宅建業法では、不動産会社が売主になる場合は、消費者保護のために解約手付になると定めています。
大きな協会に加入している不動産屋さんであれば、売買契約書に「手付金が解約手付である」と記載されていますから、「推定」する必要がありません。
(公社)全日本不動産協会の書式を見てみましょう。不動産売買契約条項の第14条(手付解除)という箇所になります。
まずは、売主さまが不動産会社ではない場合の契約書です。
1. 売主および買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行の着手の有無にかかわらず、互いにその相手方に書面により通知して、本契約を解除することができます。
2. 売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄します。
次に、不動産会社が売主になる場合の契約書です。
売主および買主は、その相手方が本契約の履行に着手するまでは、互いに書面により通知し、買主は、売主に対し、手付金を放棄して、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を買主に支払うことにより、本契約を解除することができます。
どちらも「手付放棄」「手付倍返し」で契約を解除できると定められていますね!
手付金の妥当な額・法律の規制・保全措置
手付金は大きなお金になりますから「どれくらい支払えばいいの…?」と不安になりますよね。そこで、不動産取引の慣習・法律の規制などをまとめておきます。また、手付金額が高額になった時の保全措置に関しても解説しますので知っておきましょう。
【1】手付金額に関する法律の規制
不動産会社(宅建業者)が売主になる場合でなければ、手付金額は当事者が自由に決められることになっています。手付金0円での契約もできますし、手付金を2,000万円としても構わないわけです。
不動産会社が売主になる場合は、売買代金の20%を超える手付金を受領してはいけないと宅建業法で定められています。上限があるのはこの規制だけになります。
なお、手付金0円で契約をしてしまうと、売主さま・買主さまのどちらも手付解除をすることができなくなります。万一のことが起こるリスクを考えると、ゆめ部長ならこのような契約は絶対にしません!皆さまもご注意ください。
【2】手付金の保全措置
不動産会社が売主になる契約では、次の金額を超える手付金を受領する場合、保全措置を講じるように義務付けられています。
完成物件…
物件価格の10% または 1,000万円を超える場合
例)5,000万円の物件なら500万円を超えたら保全措置
3億円の物件なら1,000万円を超えたら保全措置
未完成物件…
物件価格の5% または 1,000万円を超える場合
例)5,000万円の物件なら250万円を超えたら保全措置
3億円の物件なら1,000万円を超えたら保全措置
売主の不動産会社は保全措置を講じるのがメンドウなため、実務では、上記の金額を超える手付金を受領しないのが一般的です。
保全措置の方法は、完成物件と未完成物件で少し違いがあります。
完成物件
3つの内どれか1つを選びます。
■ 銀行等による保証
■ 保険事業者による保証保険
■ 指保管機関による保管
「指定保管機関による保管」の対象となる取引は【1】~【4】の条件を満たした場合に限られます。
【1】売主:宅建業者
【2】買主:一般消費者
【3】完成物件
【4】手付金等の合計金額が売買代金の10% or 1,000万円超える
未完成物件
2つの内どれか1つを選びます。
■ 銀行等による保証
■ 保険事業者による保証保険
宅建業法41条では、手付金「等」の保全措置と書かれています。「等」と書かれているのは、手付金だけでなく、内金・中間金も含まれるという趣旨です。売買契約の後日に中間金を受け取り、上記の制限を超えてしまったら、売主の不動産会社は保全措置を講じることになります。
たまにですけど…「手付金を不動産会社へ預けるのは不安だから、保全措置を講じる義務が発生する金額を支払いたい。」という要望を受けることもありますが、ゆめ部長の経験では、相手の不動産会社に断られます。「信用できないなら契約しなくていい。」そんな考えの不動産会社が多いんですよね…。
なお、長い間この仕事に携わっていますけど、手付金の保全措置を講じた案件は1度しかありません。あまり経験しないことなので、詳細は気にしなくて良いと思います。
【3】比較的少額な手付金等を保証する「一般保証制度」
売主である不動産会社に支払う「手付金」
取引をサポートする仲介会社に支払う「仲介手数料」
これらのお金を支払う場合、
不動産会社や仲介会社が倒産してしまったり
契約解除したいのに返金されなかったら…
そんな不安や心配があると思います。
そこで!
上記【2】の保全措置を講じる必要がない場合でも、
お客さまを守る制度があります。
参考に、不動産保証協会(ウサギ)の「一般保証制度」の紹介ページを貼っておきますので興味があれば読んでみてください!
ゆめ部長は1度も手付保証を利用したことがありません。大手仲介会社の中には、保証制度があった記憶がありますので、時間がある時に勉強して記事にしたいと思います。
【4】住宅ローンの残債 > 売買金額 (売却してもローンが残る)場合
不動産価格が高騰している時期にマイホームを購入した場合や、不動産会社が仕入れた物件が長期間売れ残っている場合などは、売買対象の不動産に設定されている抵当権の金額が売買金額よりも高く、売主さまが自己資金を支出しなければ残債を返済できないことがあります。
抵当権(ていとうけん)というのは、お金を融資した銀行が不動産に設定(登記)する権利です。もし、融資金額の返済を受けられない場合、銀行は不動産を競売にかけ、売却したお金から優先的に融資したお金の返済を受けられるというものです。
例えば…10年前に住宅ローンを6,000万円組み、6,000万円のマンションを購入しましたが、家庭の事情で売却することになったとします。現在、住宅ローンの残債が4,500万円残っていますが、売却価格は残念ながら4,000万円でした。
諸費用などをムシして単純に考えると、4,500万円-4,000万円の500万円を捻出して支払わなければ住宅ローンを一括返済できません。住宅ローンの返済をできない=抵当権を抹消できない=売却できない…ということになります。
売主さまはお金に困っている可能性が高いわけですから、高額な手付金を預けるのは少し心配になりますよね…?そこでこのような場合は、仲介をする不動産屋さんが預り証を発行して、残代金決済(=引渡時)まで手付金を預かるのが一般的です。
2020年7月30日追記…
手付金の預り証は、売主さま・買主さまのどちらに発行すればいいのか??という問題がありますけど、これは、仲介会社が売主さまに対して発行します。売主さまが手付金を受領することで手付契約も成立するわけですから、買主さまに対して発行してしまうと、手付金の授受があったとは認められませんよね。
もし、買主さまに預かり証を発行した場合、次の問題も生じます。
買主さまが手付金を用意できなかった場合、仲介会社が手付金を「預かったことにしてあげる」ことができてしまいます。これは、宅建業法第47条第3項「信用の供与」に該当する可能性があります。(追記・終)
皆さまの不安を解消し、安心・安全な取引を実現すること。これも、不動産屋さんの大事な仕事だと言えますね。
【5】手付金の妥当な金額
手付金は「やっぱ、や~めた!」という自己都合のキャンセルを認めるためのものですから、金額が高すぎるのも、安すぎるのも良くありません。
ゆめ部長がよく契約する中古物件は完成物件と同じ扱いになります。不動産会社が売主になる物件では手付金を10%以内で設定するのがほとんどですから、売主さまが個人の物件でも、同様に10%以内に抑えるのが一般的です。
実務では手付金を5%程度で設定することが多いです。5,000万円の中古マンションであれば、5%の250万円前後…200万円とか300万円が多いですね。
ところが、5%~10%の高額な手付金を要求したり、自己資金が多いなら10%でなければダメ!という不動産屋さんもいます。なぜ手付金を高額にしたいのか…その理由も教えちゃいますよ!
不動産屋さんは手付解除になっても仲介手数料を請求する権利があります。なぜなら、売買契約締結時に仲介手数料の請求権が発生しているからです。
しかし、実務では手付解除になると半金の仲介手数料しか受領できないことがありますから、不動産屋さんは気軽に手付解除されないように手付金額を高く設定しておこう!と考えています。
お客さまのためではなく、自分たちが確実に仲介手数料をもらうためなんですね。
だから、あまりにも高い金額の手付金を要求されたら、勇気をもって断るようにしましょう。他のお客さまと競合していて「交渉を有利にするために手付金は高くても仕方ない…」などの事情がなければ、手付金10%は高すぎると思います。
なお、自己資金が少ない場合や、急な契約で手付金の用意が難しい場合は、50万円~100万円で契約することもあります。最初の方でも書きましたが、分割払いは認められませんのでご注意ください!
【6】少額手付契約の注意点
「手付金を50万円も用意できません…。」ということだってありますから、少額な手付金で契約することの注意点もまとめておきます。
10万円とか、30万円とかの少額な手付金で契約を締結したい場合、売主さまが承諾すれば有効に成立させることができます。しかし、10万円であれば「やっぱ不安だから購入するのを止めよう…」と気持ちが傾きやすくなりますから、購入意欲が高くなければ、ゆめ部長はお断りしています。
それでも購入したい!というのであれば、手付解除期日を短めに設定することで対処しています。通常は、売買契約~引渡までの真ん中あたりを解除期日にしますが、2週間程度を期日にしてしまうということです。
不動産会社が売主の場合は期日を指定できませんが、個人が売主さまであれば期日を指定できるので、このような対応ができるのです。
もう1つ注意点を。
不動産屋さんが契約を急かすために「手付金はすぐに集められるだけでいいですよ!」とか「両親から20万円だけ借りてきてください!」と提案するのは、先ほど出てきました「契約締結誘因の禁止」となり、宅建業法違反になる可能性が高いと言えます。
少額手付での売買契約は、買主さまからの申出があった時だけになります。
最後に…
手付金についてよくある質問に対する回答をまとめてみました!
こうやって記事にまとめてみると、
結構なボリュームになるものですね…。
正直、ちょっと、驚きました。
読むだけでも大変なのに、
理解するのはメンドウだと思います…。
しかし!!
手付契約は大きなお金を授受するものであり、売買契約の成立要件としても大事なものですから、マイホーム売買をする前に知識を身に付けておいてくださいね!
この記事の内容を理解できていれば、売買契約の基本を理解していない営業マンや、平然と宅建業法違反をする営業マンに出くわしたとしても、自己防衛することができるはずです!
この記事が少しでも皆さまのお役に立てましたら幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
参考記事…
“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…
— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日