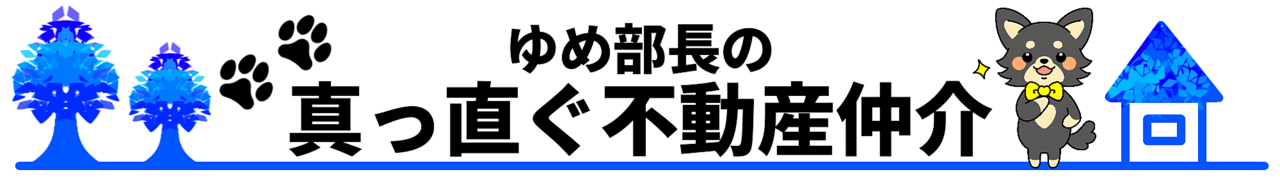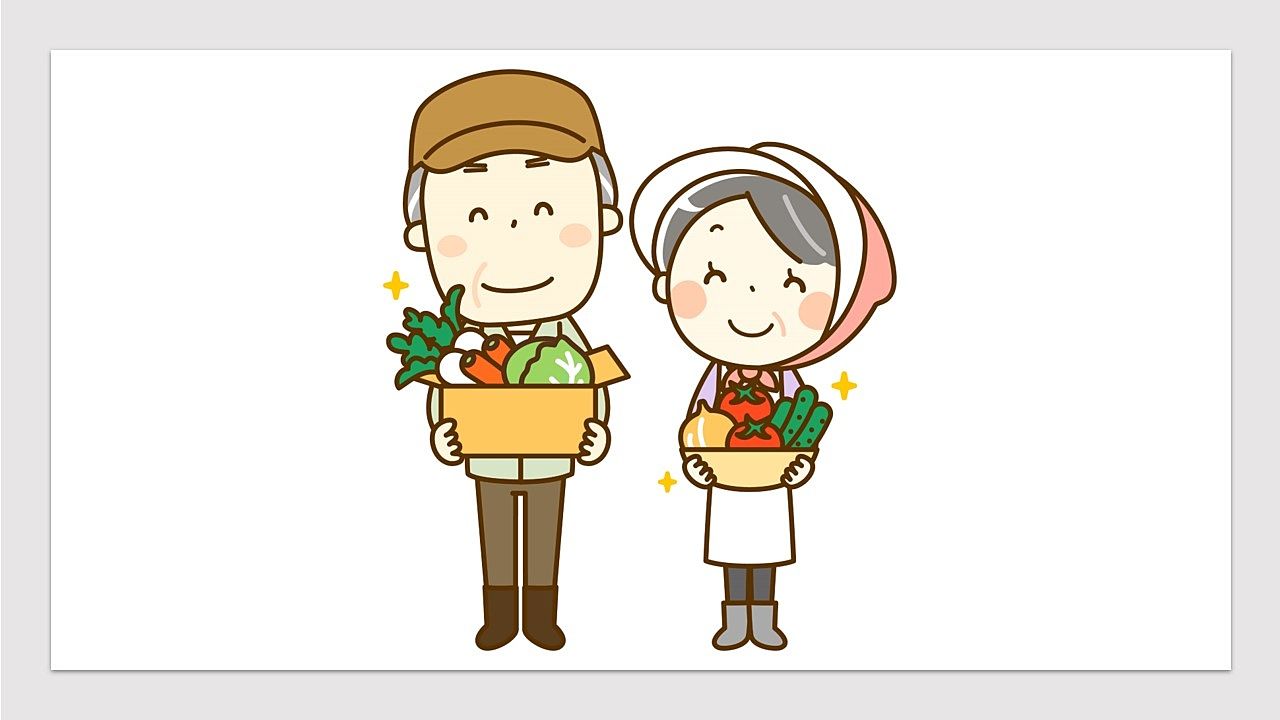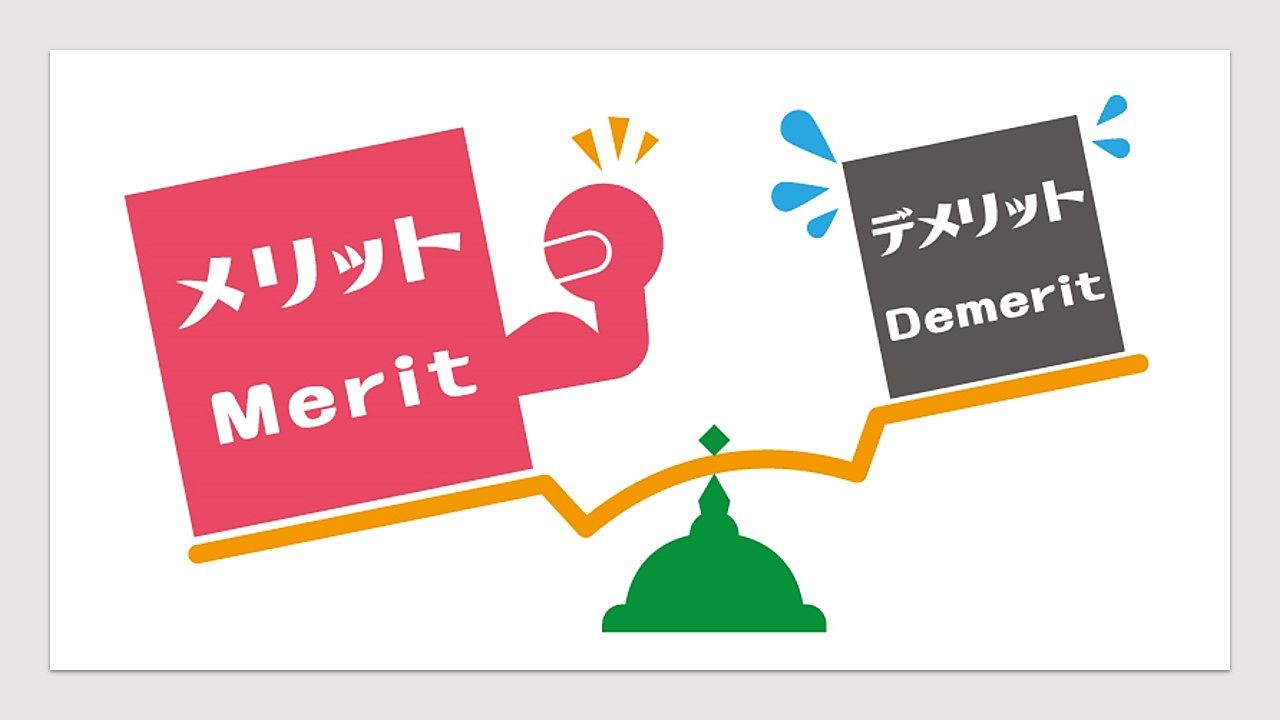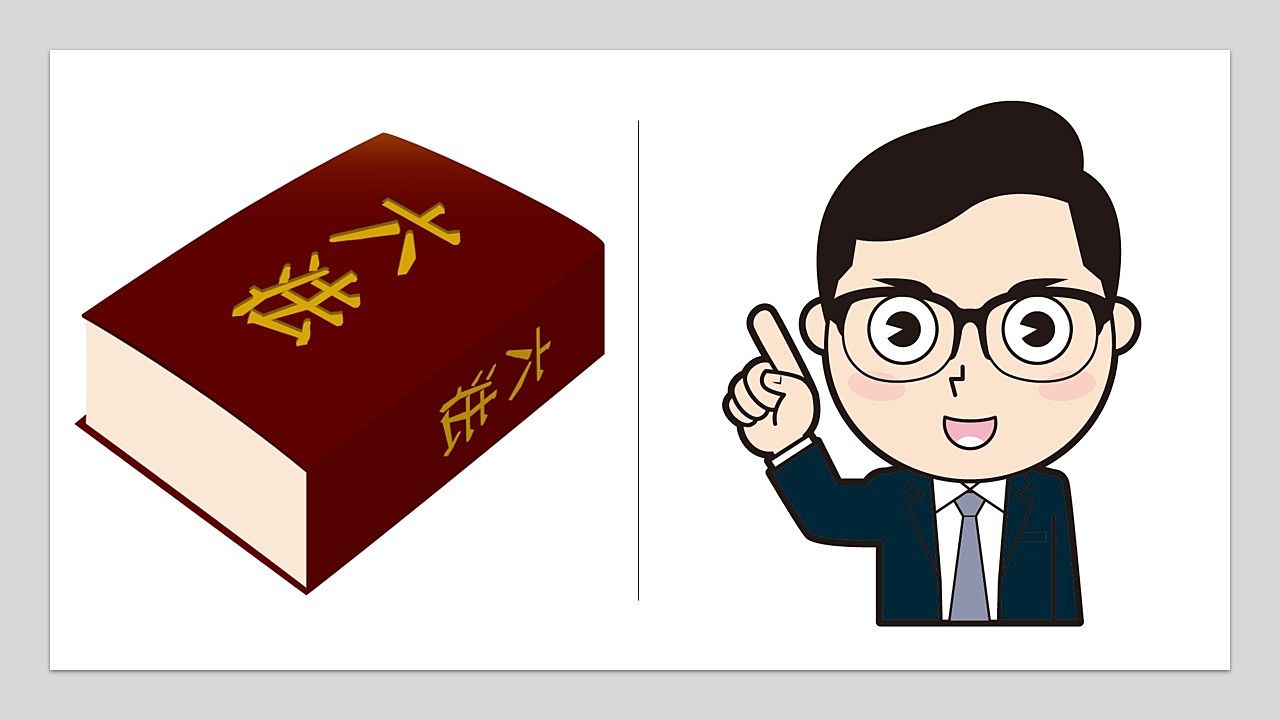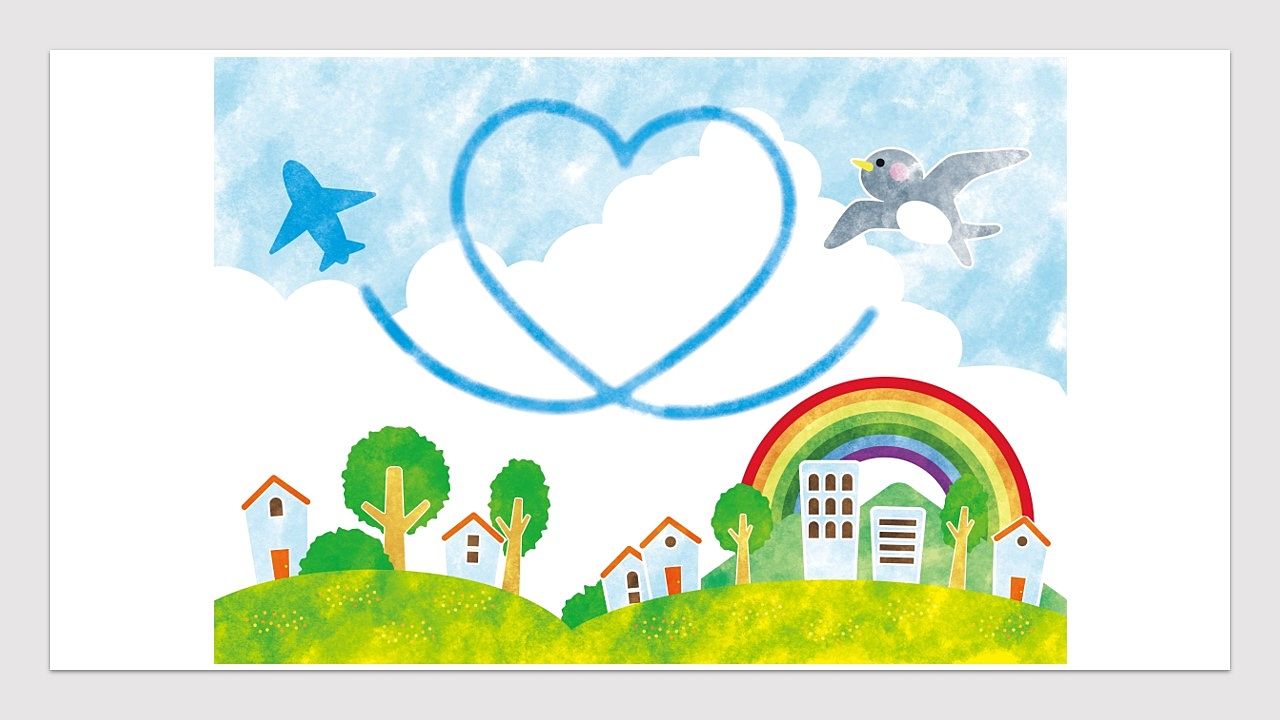生産緑地解除で不動産価格は暴落しない!「2022年問題」を徹底的に解説
2022年に生産緑地が一斉に解除されることで市場に土地が大量供給され、不動産価格が暴落するかも!?と心配されている「2022年問題」について、宅建マイスターが徹底解説します!
生産緑地に関して勉強していない人たちが「2022年以降に不動産価格は暴落する!」と安易に発言しているのが気になっています。この問題の最新情報も踏まえてわかりやすく解説しつつ、ゆめ部長の意見(大暴落はしない!)も織り交ぜてみますので参考にしてくださいね。
ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」
生産緑地地区とは…?
上の写真のように「生産緑地地区」と書かれた看板を見たことがありませんか??ゆめ部長は東京都の練馬区に住んでいるので、ちょっとお散歩するだけでいくつもの「生産緑地地区」を発見することができます。
この「生産緑地地区」とは何か…?
まずは、ここから見ていきましょう!
「生産緑地地区」とは、良好な都市環境の形成を目指し、街づくりを進めていくエリア(市街化区域)内にある農地を保全するために定められる地区のことです。
市街化区域というのは、街づくりを進めていくエリアのこと。農地を宅地に変えてどんどん住宅が建てられていきます。
農地が宅地になり、自然がなくなった街は、いったいどうなるでしょうか…?空地が少ない住宅街は災害に弱くなり、緑が少ない住宅街は安らぎと癒しがありません。これでは、人の生活は潤わないでしょう。それに、緑や畑にはいろんなメリットがあります。
たとえば…
■ ヒートアイランドの緩和
■ 食料自給率の上昇
■ 農業体験を通した食育・情操教育
■ 災害時の避難場所 etc ...
だからこそ、住宅街にある農地を「生産緑地地区」として保護し、無秩序な宅地化を防止しなければいけない!というお話になるわけです。
生産緑地が定められた経緯
「生産緑地」が定められた経緯を確認しておきましょう。
1970年頃
人口増加で都市部の農地が急速に宅地化され緑地が大幅に減少した結果、住環境が悪化し、災害が多発するという問題が生じました。
1974年
「生産緑地法」を制定して農地を保全しようと試みましたが、「土地不足」「地価上昇」を止めることができず、問題は解決できませんでした。
1992年
生産緑地法改正。宅地化の需要を満たしつつ、農地も保全するために、市街化区域内の農地は下記の2つに区分されました。
■ 保護する農地「生産緑地」
■ 宅地化を進める農地「宅地化農地」
この法改正の効果により、「生産緑地」に指定された農地は保全され、24年間で約15%しか減少せずに済みました。詳細は次の項目「生産緑地地区の広さはどれくらい?」に記載します。
一方、「宅地化農地」に指定された農地は原則通りに宅地化され、22年間で約58%減少しました。総務省「固定資産の価格等の概要調書」によると、「宅地化農地」の面積推移は次のようになります。
平成 4年 … 30,628ha
平成26年 … 12,916ha
だいぶ減少していますけど、まだ、かなりの広さが残っているのがわかりますね。
※ 1ヘクタール = 100アール = 10,000㎡
生産緑地地区の広さはどれくらい?
生産緑地地区の地区数・面積については、国土交通省の都市計画現況調査で確認することができます。
2020年1月18日時点では平成29年調査結果まで公表されていました。興味があれば、次のリンクをクリックして確認してみてくださいね。ちなみに、平成29年度のデータを確認したい場合は次の順番でクリックします。
平成29年調査結果
↓
№2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
↓
(24)生産緑地地区
参考 … 国土交通省の都市計画現況調査
3年分のデータを見ておきましょう。
平成29年
61,207地区 12,972.5ha
平成28年
61,839地区 13,187.6ha
平成27年
62,473地区 13,442.0ha
※ 1ha(ヘクタール)=10,000㎡
平成5年は15,164haなので、24年で約15%減少ペースです。
宅地化農地は22年で約58%減少していましたから、比較すると、ゆっくり減少しているのがわかりますね。
「東京ドーム○○個分」という表記をよく見るので計算してみました。
東京ドームは46755㎡だから4.6755ha
平成29年 … 2,775個分
平成28年 … 2,821個分
平成27年 … 2,875個分
2年で100個分減っています。
「ふ~ん、そーなんだ。」って感じですよね(笑)
ついでなので、東京23区で面積が広い大田区・世田谷区と比較してみます。
平成29年の生産緑地地区 … 12,972.5ha
12,975ha = 1億 2,972万 5,000 ㎡
1億㎡ = 10km × 10km
大田区面積 = 59.46 km² = 5,946万 ㎡
世田谷区面積 = 58.05 km² = 5,805万 ㎡
東京23区で、1番面積が広い大田区と、2番目に広い世田谷区の面積を合わせても、まだ負ける…という広さ!(驚)
なお、生産緑地地区は三大都市圏の市街化区域を念頭に置いた制度であるため、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・大阪府で全体の80%を占めています。東京を見てみると、23区内では11区にしか生産緑地地区はなく、山手線内側は1つもないそうです。
2021年12月28日追記…
令和2年調査結果まで公表されていたので追記します。
令和 2年:59,201地区 12,332.3ha
平成31年:59,633地区 12,496.8ha
平成30年:60,338地区 12,713.2ha
生産緑地の指定要件
生産緑地に指定されるには次の要件があります。
■ 現に農業の用に供されていること
■ 良好な生活環境確保の機能を有すること
公共施設等の用地として適していること
■ 面積が一団で500㎡以上の農地であること
※ 条例で300㎡以上に緩和することができます。
■ 農業の継続が可能であること
※ 原則として30年間の営農の意志があること。
1992年の生産緑地法改正で「生産緑地」に指定された農地は、30年後の2022年までは農業を継続してね!という制限が付けられました。この2022年がついにやってきたわけです。
生産緑地の写真を確認してみてください ↓ ↓ ↓
写真を見ると指定要件が頭に入りやすいと思います!
生産緑地の指定解除
生産緑地の指定が解除できるのは次のケースに限られています。
■ 生産緑地指定後30年経過
■ 主たる従事者が死亡。相続人が農業を営まない。
■ 主たる従事者が疾病・障害等で農業の継続が困難
これは、結構、厳しい条件だと思います。
農家は「高齢化」「後継者不足」「収益性が低い」という問題を抱えているそうです。収益性が低くて後継者がいない。高齢になり体力的にキツイ。でも、農業をやめられないってことですからね…。
「農家がカワイソウじゃないか!」と心配しなくて大丈夫です!あとで解説しますけど、この問題を解決できるように法律が改正されました。
次に、指定解除の流れを確認しましょう。
市町村長に時価での買取申請
↓
予算不足で買い取りNG
↓
農林漁業希望者へのあっせん
↓
あっせん不調
↓
生産緑地解除
なお、生産緑地を解除する手続きだけでも約3ヶ月かかります。
生産緑地が解除された場合の注意点!
注意点1…
猶予されていた相続税に利子税を加算して納税しなければいけません。利子税はかなりの額になりますし、売却した際の利益には譲渡税(所得税・住民税が)も課税されてしまいます。多額なお金を用意できるか…税理士先生へ相談する必要があるでしょう。
注意点2…
固定資産税・都市計画税の減税もなくなります。激変緩和措置があるため、本来の税額になるのは5年後です。(毎年20%ずつ上昇)
生産緑地指定 農家のメリット・デメリット
農家が生産緑地地区の指定を受けると、税金の優遇を受けられるメリットがあるけど、「売れない」「貸せない」「建てられない」というデメリットがあると言われてきました。
この記事は「生産緑地2022年問題で不動産価格は暴落するか?」というテーマで執筆していますので、難しすぎる内容は省略して、生産緑地地区に指定された農家のメリット・デメリットを簡単に解説します。
メリット
1. 固定資産税・都市計画税の減額
生産緑地の多くは三大都市圏の市街化区域に指定されるとお話しましたね。三大都市圏の市街化区域は不動産価値が高く、固定資産税・都市計画税の課税額はかなり高額になります。
しかし、「生産緑地」に指定された農地であれば、固定資産税と都市計画税を計算する際の「評価」と「課税」が一般農地と同じようになり、大幅に減額されます。
「宅地化農地」が「農地課税」になると、固定資産税が 1/100 ~ 1/300 になるそうです。たとえば、東京23区内の生産緑地地区で「農地課税」になる場合、500㎡あたりの固定資産税・都市計画税の年税額は2,000円くらいになると聞きました。(場所によると思います。また、固定資産税評価額が上がっているため、2022年以降はもう少し上がるかもしれません。)
2. 相続税の納税猶予
生産緑地を相続や遺贈(遺言による贈与)により取得して引き続き農業を営む場合、相続税の大部分が納税を猶予されます。また、将来、相続人が死亡した際には、猶予されていた税額が全額免除されます。
なお、生産緑地指定から30年経過したことを理由に生産緑地の指定解除した場合、猶予されていた税額は免除されません。それだけでなく、相続税に利子税を加えて課税されますし、30年前は不動産バブルで土地の評価額が高いため、課税額が高額になることに注意が必要でしょう。
デメリット
生産緑地に指定されると農家には次のような義務が課せられます。
■ 農業を30年間も営む義務がある。
■ 農地として管理する義務がある。
■ 建築物や工作物の新築、改築、増築の禁止
■ 生産緑地の標識を設置する義務がある。
これらの義務から生じる三重苦…
「売れない」
農業を30年営まないと生産緑地を解除できず売却できませんでした。2022年には30年経過する生産緑地がたくさんありますけど、ほとんどの生産緑地が新制度の「特定生産緑地」の指定を受けて10年延長するようです。なお、多くの農家が「相続税の納税猶予」を受けているため、売却時の納税額が高額になり、10年経過した後も簡単には売却できないはずです。
「貸せない」
農地を貸してしまうと、農地法により賃貸借契約が自動更新されるため、自己都合で返却してもらうことができませんでした。しかし、2018年9月に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)」が制定され、賃貸借契約が自動更新されなくなりましたので、今は「貸せない」というデメリットは解消されています。
「建てられない」
生産緑地法第8条で「建築物や工作物の新築、改築、増築の禁止」が定められているため、不動産所得を得るためにアパートなどを建築することはできません。ただし、2017年の生産緑地法改正により、地元の農産物を使った商品の製造・加工・販売のための施設やレストランであれば建築できるようになりました。
農家のデメリットを解消することで農地を保護する方針に変わっていることがわかると思います。これからの時代は、農地を保全することで、自然と触れ合える緑豊かな街づくりが進められていくことでしょう!
2017年の生産緑地法改正
2017年の生産緑地法改正は3つのポイントがあります。
ポイント1…
生産緑地地区の面積要件(500㎡以上)が緩和され、市区町村が条例で300㎡以上に引下げできるようになりました。500㎡の生産緑地があった場合、300㎡だけ農地として残し、残りの200㎡に自宅を建築することが可能になったわけです。地主さんにはありがたい改正だと言えるでしょう。
多くの生産緑地地区を持つ、練馬区・世田谷区のWebページを確認してみましたら、どちらも300㎡以上でOKになっていました。
ポイント2…
生産緑地地区内において下記の建築物を設置できるようになりました。
■ 農作物等加工施設
■ 農作物等直売所
■ 農家レストラン
これなら、農家が収益を上げやすくなりそうです。
ポイント3…
生産緑地地区として指定されてから30年経過した農地について、買取り申出可能時期を10年延長できる「特定生産緑地制度」が創設されました。再々延長まで認められて20年延長できるため、農家の選択肢が増えたと言えますね。
「特定生産緑地」に指定されれば、
■ 固定資産税・都市計画税の減税(農地課税)
■ 相続税納税猶予制度
この2つの特典が継続になります!
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)
2018年に施行されたこの法律で生産緑地を人に貸しやすくなりました!2つのポイントを確認しましょう。
ポイント1…
農地法の法定更新が適用されません!「農地を貸してしまったら返してもらえない…」そんな悩みを解決できるようになりました。
ポイント2…
相続税納税猶予制度は継続されます!生産緑地は農地として管理する義務があり「人に貸してしまうと相続税の納税猶予が受けられなくなる…」という問題がなくなりました。
生産緑地は固定資産税などのランニングコストと管理する手間ががかかります。しかし、人に貸すことで管理せずに収益を生むことができるようになりました。最近は「シェア畑」などの市民農園が人気を集めていますよね!
参考に写真を掲載しておきます ↓ ↓ ↓
「生産緑地 2022年問題」とは…
ここまでの知識を使って「生産緑地2022年問題」をまとめます。
1992年に生産緑地に指定され、2022年に30年の期限を迎える農地は、約13,000haのうち約80%の10,000ha強もあります。
もし、この10,000ha(1億㎡=約3,000万坪)全てが生産緑地を解除した場合、市区町村が買い取ったり、農林業希望者へあっせんできるのは少数でしょうから、かなりの土地が市場に出回ることになります。
三大都市圏にある好立地の生産緑地地区が宅地として一斉に市場へ開放されれば、住宅供給が増え、空き家問題はさらに深刻化するのは間違いありません。また、一気に需要を上回る土地が供給されると土地価格が暴落する可能性も否定できないでしょう。
これが「生産緑地2022年問題」と 言われていた ものです。
「言われていた」と書いた理由を説明します。
理由1…
2018年に生産緑地法が改正され「特定生産緑地指定制度」が創設されました。この制度により、30年経過した生産緑地地区は買取申出可能時期を10年延長できます。さらに、10年後に再延長も可能ですから、農家が生産緑地を解除せずに農地を保全する選択肢ができたわけです。
理由2…
多くの農家が生産緑地のメリット「相続税の納税猶予制度」を利用しています。もし、30年経過して生産緑地を解除してしまうと、猶予されていた「相続税」と猶予期間の「利子税」を支払わなければいけません。30年前はバブル期で土地価格が高い時期ですから、この時期の土地評価額に対して課税される相続税は相当高額になるはずです。また、売却した利益に対する譲渡税もかなり負担が大きく感じられるでしょう。
理由3…(2021年12月28日追記)
令和3年9月の国土交通省のデータ「特定生産緑地指定状況」によると、東京都の生産緑地 2428haの内、2186ha(全体の90%)が、特定生産緑地の「指定済み・指定見込み」になっています。つまり、宅地化されず農地のまま残るということですね!
ゆめ部長の結論!
2022年に土地が大量に供給され、需給バランスが崩れることで不動産価格が「暴落」する…という社会問題には発展しないでしょう。逆に、山手線内側には生産緑地がないわけですから、都心部の地価はまだ上昇し続ける可能性が高いのではないでしょうか。人口減少が進みながらも、格差拡大が加速していけば、都心部に人気が集中しますよね。
安易にアパートを建築しないで!
生産緑地が解除された土地は立地条件が良いため、次のような需要が見込まれます。
■ 一戸建て
■ マンション
■ アパート
■ トランクルーム
■ ビル(店舗・事務所)
■ 駐車場
■ 社会福祉施設(自治体があっせん)
■ 市民農園(国土交通省・市民農園等整備事業)
などなど。
生産緑地解除を営業チャンスとみて、「アパートを建築して収益をあげましょう!」という提案をする不動産会社がたくさん出てくることでしょう。
しかし、日本は「人口減少・少子化・超高齢社会」という大問題を抱えていますから、これ以上、賃貸住宅を増やしたところで供給過剰になるのは間違いありません。
今後の賃貸需要も予測したうえで「不動産の最有効使用」する方法を不動産のプロと検討してみて欲しいと願っています。
最後に…
国や自治体が生産緑地の減少を食い止める対策を検討するようになりました。市民農園の需要が高まっていることからもわかる通り、緑地を残してほしいと考える住民が増えた結果、生産緑地は「保全」から「活用」する時代になってきたのでしょう。
これからの不動産取引を考察するためには重要な知識になるテーマですから、もっと勉強して記事の内容をパワーアップさせていく予定です。これから数回は記事のリライトを行いますので、興味を持っていただけたら、また読みに来てくださいね。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
フォロー・チャンネル登録してくださいね!
■ 2020年08月03日 投稿
■ 2021年12月28日 更新
“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…
— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日