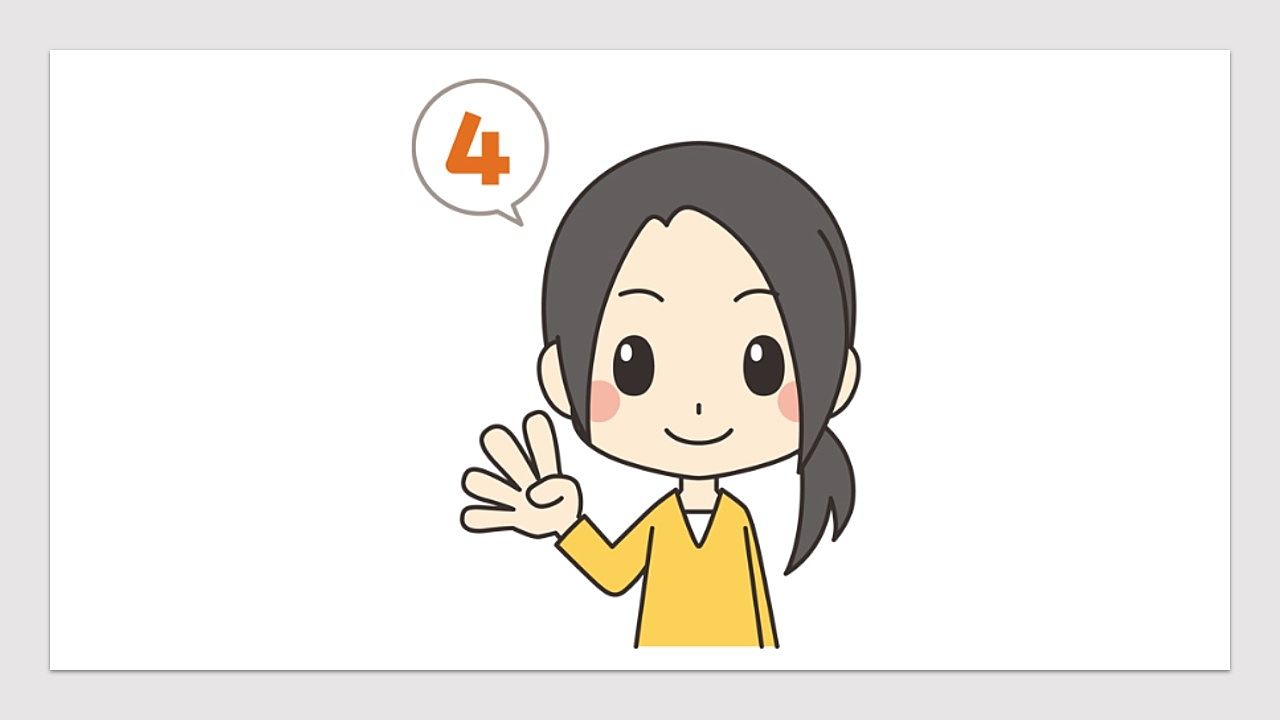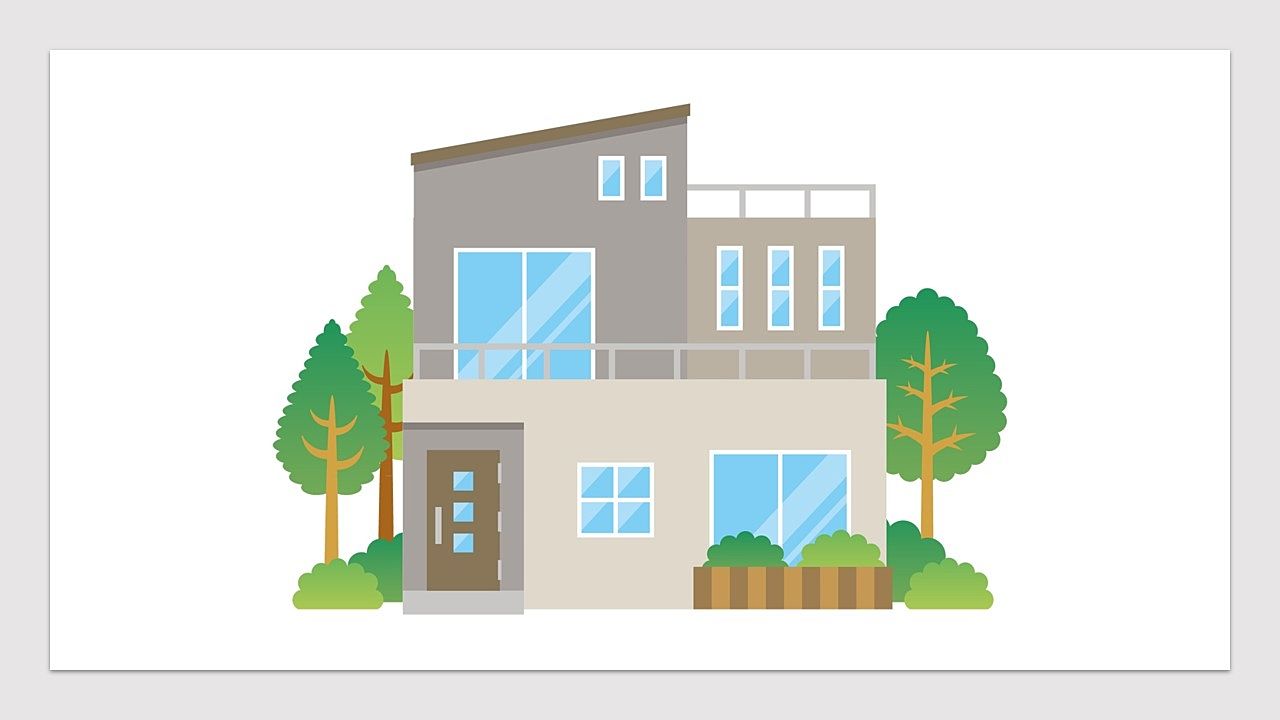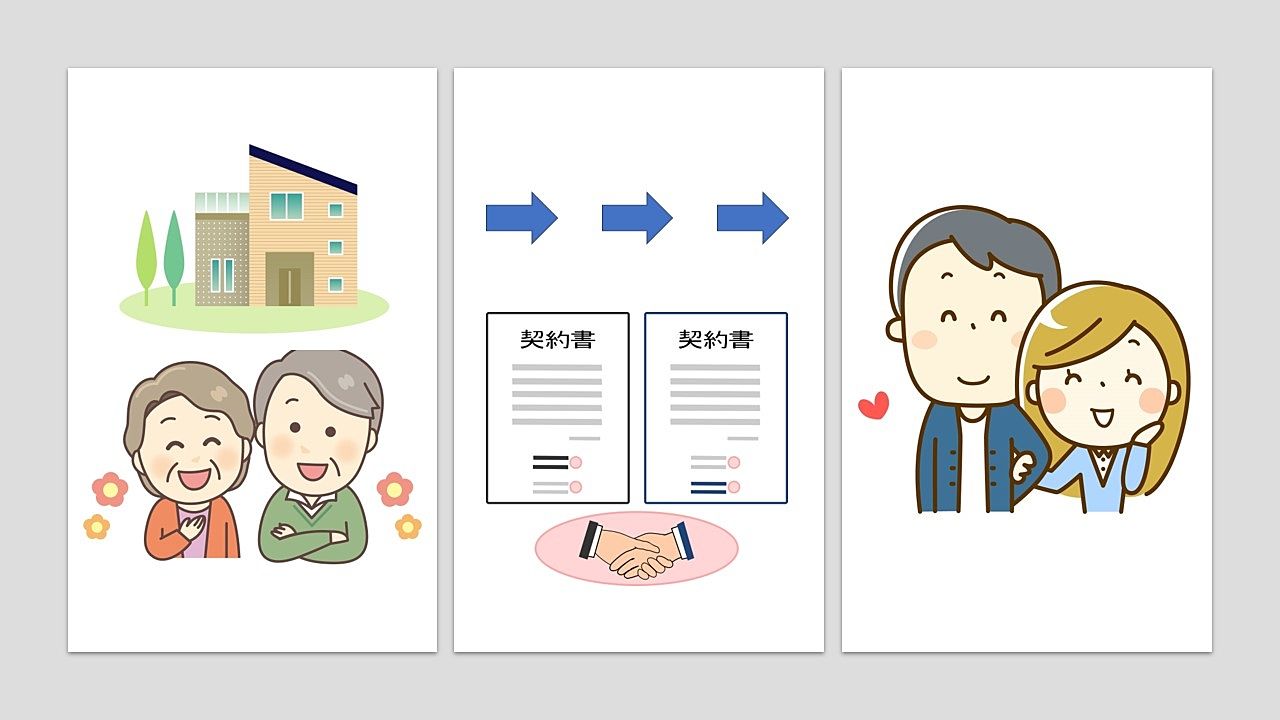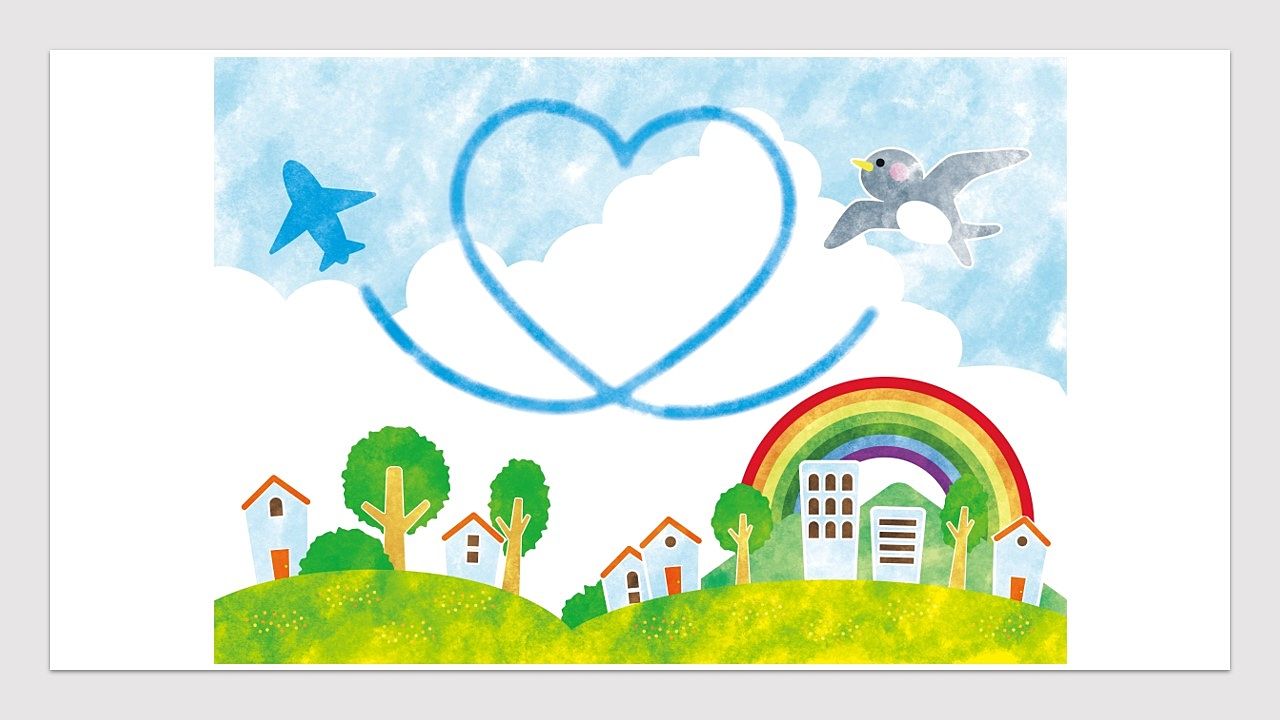不動産売買契約の「登録免許税」を解説!
不動産を売買する際に行う「登記」に税金が課税されるっことを知っていますか?登記費用の見積もりをよく見ると、司法書士先生の報酬よりも「登録免許税」という税金が多いことに気が付くはずです。今回の記事では登録免許税に関してまとめてみますね。
ブログ執筆:上級宅建士「ゆめ部長」
不動産売買の登記で課税される登録免許税とは…?
登録免許税とは…「登記」することに対して課税する税金です。税金はメリットがあることに対して課税されるわけですけど、じゃあ「登記」はなんのために行うのでしょうか。まずはココを見てみましょう!
不動産は高額なものですから、安心して売買するためには「誰が所有者なのか?」がわからなければ、怖くて取引することができませんよね。そこで、不動産の「所在・面積・所有者など」を「登記簿」へ記録して一般公開するようになっています。
不動産の所有者が「この不動産の所有者は私ですよ~」と登記すれば「権利者が第三者へ対抗できるようになる」というメリットが生じます。
ちょっとわかりづらいですよね(汗)
簡単に解説すると…
例えば、ゆめ部長が、Aさん・Bさんの2人へ同時に不動産を売却したとしましょう。(ブラックゆめ部長登場!)
これを「二重売買」といいますけど、この場合、Aさん・Bさんのどちらが権利を主張できるか…?という問題に対して、民法は「登記をして対抗力をつけた人を優先する」と定めています。
つまり、
Aさんが先に登記をすればAさんの勝ち!
Bさんが先に登記をすればBさんの勝ち!
となるわけです。
このように、登記にはメリットがあるから課税する!ということなのでしょう。
ちなみに…
この対抗力をつけるための登記には強制力がありません。権利を主張したかったら自己責任で登記してね。ということになっています。登記をしない人を見たことはないですけど、トラブル防止のために登記が重要だということは押さえておきましょう。
もう1つ。個人情報の塊に思える登記簿の内容は、だれでも法務局で取得することができるようになっています。個人情報保護と不動産取引の安全性を天秤にかけた結果、「不動産取引の安全性」がより重要なため、登記簿を一般公開することはやむを得ない…ということです。
不動産を売買する際に行う登記は全部で4つ!
■ 表題登記
■ 所有権保存登記
■ 所有権移転登記
■ 抵当権設定(抹消)登記
登記事項証明書を見たことがない人の方が多いはずですから、法務省の見本を一緒に見てみましょう。それぞれの登記がどこに反映されるのか…?を確認してください!
表題登記【不動産売買の登記1】
表題登記というのは、「建物がこの世に生まれましたよー」という最初の登記のことで、種類・構造・床面積・建築年月日などが記載されています。赤ちゃんが生まれた時の出生届け(しゅっしょうとどけ)のようなものですね。
上の「登記事項証明書・見本」の表題登記の部分を見てください。
新築物件の場合、この表題登記を建物建築後1か月以内に行う義務があります。この義務に基づいて「土地家屋調査士」先生が登記を行うと、その不動産に関する建物の登記事項証明書が誕生します。(上記画像の緑色の紙です。)この段階では、甲区・乙区がないため、表題登記の部分しかない寂しい感じの書類になります。
この登記は法律で義務付けられたものですから税金は非課税。登録免許税はかかりません!もちろん、土地家屋調査士先生の報酬は必要ですよ。建売住宅の契約をすると、8万円~12万円プラス消費税という感じで請求されます。
所有権保存登記【不動産売買の登記2】
所有権保存登記というのは、権利部(甲区)に初めてされる登記のことです。「建物の親(所有者)は私です!」と主張するための登記で、所有権保存登記を行うと甲区ができあがります。
上の「登記事項証明書・見本」の所有権保存登記の部分を見てください。
新築一戸建てを購入すると、売買契約が終わってから表題登記を行い、残代金決済日(=引渡日)に、所有権保存登記と抵当権設定登記を行うことになります。
所有権保存登記の登録免許税をチェックしましょう~~
税率は0.4%ですが、次の要件を満たすような住宅であれば軽減税率が適用されますから、税率が0.15%になります!(62.5%OFF)
■ 自己居住用住宅
■ 新築(注文住宅)または取得後1年以内に登記完了
■ 登記事項証明書記載の床面積が50㎡以上
注意点を解説します。
「新築日」は表題部の日付を確認してください。
登記事項証明書記載の「床面積」はマンションだと注意が必要です。分譲時パンフレットに記載された面積は「壁芯面積」で、登記事項証明書に記載された面積は「内法(うちのり)面積」になります。
よくわからないですよね…(汗)
壁芯面積:壁の中心部分を含む面積
内法面積:壁の内側までの面積
壁芯面積 < 内法面積 となるので、
面積の確認は分譲時パンフレットではなく
登記事項証明書(謄本)で行ってください。
なお、認定長期優良住宅 または 認定低炭素住宅なら、税率は0.1%になります!なかなか出会わないですけど、今後は省エネ住宅が増えていくため目にする機会が増えるかもしれませんね。
※ 税率0.4% ⇒ 0.15% ・ 税率0.4% ⇒ 0.1%
税率軽減は令和6年(2024年)3月31日まで
次に、何に対して税率をかけるのか…?という問題です。
これは「法務局の認定価格」に対して…になります。東京法務局管内・新築建物課税標準価格認定基準表(令和3年4月1日以降)によると…
木造の戸建て … 102,000円/1㎡
RC造の戸建て … 158,000円/1㎡
木造共同住宅 … 110,000円/1㎡
RC造の共同住宅 … 158,000円/1㎡
となっています。
参考サイト…
不動産登記における評価額のない建物の課税標準について(東京法務局)
参考資料…
木造一戸建て・建物面積が100㎡で軽減税率の有・無を比較してみましょう。
無:102,000円×100㎡×0.40%=40,800円
有:102,000円×100㎡×0.15%=15,300円
差額は25,500円
所有権保存登記だと、軽減税理の有無で大きな違いはありませんね。
所有権移転登記【不動産売買の登記3】
所有権移転登記というのは、不動産を売買した際に、所有権が売主さまから買主さまへ移ったことを公示するための登記です。
上の「登記事項証明書・見本」の所有権移転登記の部分を見てください。
先ほども解説しましたけど、第三者に対して「私が権利者ですからね!」と主張するために必要な登記ですから、登記は必ず行ってください。
登録免許税を見てみましょう~
土地の売買を行った場合…
固定資産税評価額に対して税率をかけます。
令和5年3月31日まで:1.5%
固定資産税評価額というのは、毎年6月になると不動産の所有者へ郵送される「固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書」に記載された金額です。あるいは、都税事務所で取得できる「評価証明書」「公課証明書」にも記載されています。実際の取引価格の大体70%くらいになると言われていますけど、エリアによっては大きくズレていることがあります。
建物(中古)の売買を行った場合…
固定資産税評価額に対して税率をかけるのは土地と同じです。
税率:2%
下記条件を満たす住宅:0.3%
■ 自己居住用住宅
■ 取得後1年以内に登記完了
■ 登記事項証明書記載の床面積が50㎡以上
■ 登記簿の新築日が「昭和56年12月31日以前」
上記を満たさない場合でも、次の場合はOK
・耐震基準適合証明書を取得
・既存住宅売買瑕疵保険へ加入
・住宅性能評価書あり(耐震等級1・2・3)
登記簿の新築日が「昭和56年12月31日以前」のマンションや戸建を購入するのであれば、「耐震基準適合証明書」を取得できるか確認するとよいでしょう。
参考記事…
中古住宅の建物に関しては、登録免許税の軽減を受けられるかで大きな違いが出てきます。実際に計算してみましょう。
固定資産税評価額1,000万円の建物に関して軽減の有・無を比較します。
無:1,000万円×2.0%=200,000円
有:1,000万円×0.3%=30,000円
差額は170,000円(-85%!)
戸建てと比べてマンションは建物が占める割合が大きいので、耐震基準適合証明書を取得できるかどうかは大きなポイントになります。築年数が経過している不動産を売却する場合は、高値成約を勝ち取るためにも、耐震基準適合証明書を取得できるかどうかを事前に確認してくださいね。
※ 建物の軽減は令和6年3月31日までです。
売買ではなく、相続・遺贈・贈与で不動産を取得した時は次の通りです。
相続:0.4%
遺贈・贈与:2%
抵当権設定(抹消)登記【不動産売買の登記4】
抵当権設定登記とは…銀行からお金を借りる際に、購入する不動産に対して銀行が設定を求める登記です。抵当権が設定された不動産にかかわる住宅ローンを返済できなくなった場合、銀行は不動産を競売にかけ、他の債権者に優先して融資したお金の返済を受けることができます。
上の「登記事項証明書・見本」の抵当権設定登記の部分を見てください。
抵当権は権利部(乙区)に記載されます。この抵当権を抹消できないと不動産を売却できません。まぁ、売却はできますけど、誰も購入しません。なぜなら…抵当権が残っていたら、売買代金を支払って所有権を取得した後に、抵当権が実行されて競売にかけられた場合、せっかく取得した所有権を失うからです。
では、登録免許税を見てみましょう~
債権金額に対して税率をかけます。
税率は0.4%ですけど、先ほど見た建物(中古)の所有権移転登記と同じ条件を満たすのであれば、税率は一気に75%OFFの0.1%まで軽減されます。
なお、要件は「建物(中古)の売買を行った場合…」と同じです。
具体例で計算してみましょう。
皆さまが住宅ローンを4,000万円借りてマイホームを購入したとして、軽減の有・無を比較します。この場合、債権金額は4,000万円です。
無:4,000万円×0.4%=160,000円
有:4,000万円×0.1%=40,000円
差額は120,000円(-75%)
抵当権設定登記も登録免許税の軽減を受けられるかどうかで大きな差が出ましたね!
最後に…
登録免許税って、難しくて、なんだかよくわからない税金だと思いますけど、結構な金額を納税しなければいけません。しかし、軽減を使うことができれば大幅に下げられる税金でもあります。
不動産屋さんは「耐震基準適合証明書」の威力を理解していないことが多いので、不動産を購入するならこの知識は必須だと思います。また、不動産を売却する際も、この知識があれば高値成約を目指せる可能性が上がりますね。
なお、「耐震基準適合証明書」があると、住宅ローン控除も利用できるようになってしまう特典付きなんですよ!
勉強する価値あり!だと理解してもらえましたか!?
というわけで、本日のお話はここまでです!
この記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。
“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…
— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日